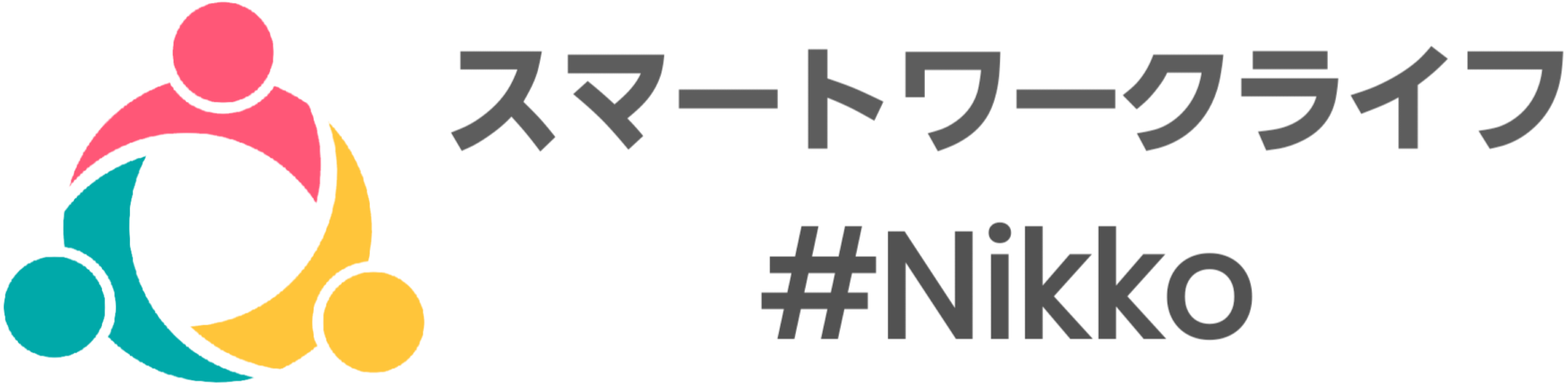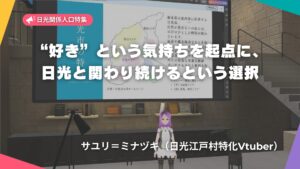ワーケーションの“壁”:日光で見えてきた課題

こんにちは!スマートワークライフ#Nikko(スマ日)で活動しているJHです。
自然豊かな環境で仕事と休暇を両立する「ワーケーション」。企業の働き方改革や個人のライフスタイル多様化を背景に、その取り組みは全国各地で広がっています。日光も例外ではなく、世界遺産・温泉・自然を備えた魅力ある地域として、多くの企業や個人を受け入れてきました。
しかし、実際に体験してみると「理想と現実のギャップ」が少なからず存在します。今回は、実際に聞いた意見や事例を交えつつ、ワーケーションのデメリットを「個人・企業・地域」の3つの視点から整理し、より良い形で実践するためのヒントを考えていきます。
個人にとっての課題
① オン・オフの切り替えの難しさ
ワーケーションの大きな魅力は、観光地に滞在しながら働けることにあります。しかし、自然や歴史に囲まれた日光では、その魅力ゆえに業務との境界が曖昧になりがちです。
実際に鬼怒川温泉に滞在したスマ日のモニターツアー参加者は「午前中は資料作成に集中しようと思ったが、窓から見える雪景色に心を奪われてしまい、結局予定が大幅にずれ込んだ」と話していました。逆に、せっかく観光地に来ているのに常にPCやスマホを気にしてしまい、「休暇を楽しめなかった」という声もあります。切り替えが難しい点は、意外な落とし穴です。
② 通信環境の不安定さ
日光市街地や一部の宿泊施設ではWi-Fi整備が進んでいますが、戦場ヶ原や霧降高原など自然の中では電波が弱くなることがあります。ある参加者は「商談中に回線が途切れ、結局市内のコワーキング施設に移動して再接続した」と振り返ります。業務において安定した通信は必須条件であり、山奥では特に注意が必要です。
③ 設備の制約
スマ日の活動拠点でもある「mekke 日光郷土センター」や「△もぐらベース」など、充実した環境を提供する施設もありますが、すべての宿泊先やカフェが業務利用を想定しているわけではありません。コンセント不足や、オンライン会議に適した空間がない場合も多いです。

④ 孤独感・コミュニケーション不足
チームで訪れる場合は交流が生まれますが、個人で参加すると孤独を感じやすいという声もあります。普段のオフィスでは当たり前の雑談や相談ができず、気分転換やモチベーション維持が難しいと感じる人も少なくありません。
企業にとっての課題
① 成果管理の難しさ
ある企業が社員研修を兼ねて日光でワーケーションを実施した際、「業務の進捗をリアルタイムで把握しづらい」という意見がありました。観光地にいるという意識が、働き手と管理者双方に“甘さ”を生むリスクがあります。オンラインでのルールを整備しなければ、効果が半減してしまうかも知れません。
② コスト負担の問題
日光は首都圏から比較的アクセスしやすいとはいえ、交通費や宿泊費、さらには会議室利用料などが積み重なると企業負担は軽くありません。福利厚生として位置づけるのか、研修費用とみなすのか、社内ルールを明確にしなければ不公平感が生じます。

③ 労務管理の課題
ワーケーションを制度化する場合、勤務時間や労災の扱い、緊急時の対応責任などを整理する必要があります。特に山間部での活動中に怪我や事故が発生した場合、労務管理上の扱いをどうするかは企業にとって大きな課題です。
地域にとっての課題
① インフラと受け入れ体制
日光市内ではコワーキング施設やWi-Fi環境の整備が進みつつありますが、紅葉シーズンや行楽期には観光客で宿泊施設が埋まり、ワーケーション希望者が予約できないこともあります。地域にとっては観光需要とビジネス需要をどう両立させるかが課題です。
② 季節変動による需要の偏り
秋は紅葉観光で賑わいますが、閑散期には滞在者が減少し、施設の稼働率が低下します。ワーケーション誘致は新たな需要を生み出す可能性がありますが、年間を通じて利用を平準化する仕組みづくりが今後の課題となります。

③ 継続性の確保
単発的なワーケーション誘致では、一度の滞在で終わってしまう可能性があります。地域にとっては、リピーターを増やし、関係人口の拡大へとつなげる仕組みづくりが不可欠です。特に、観光地を支える事業者達、または住民達にもワーケーションへの理解を深めてもらい、協力体制を築けるよう働きかけることが大切です。
ワーケーションのメリットを整理すると次の通りです。
| 対象 | 主なデメリット |
|---|---|
| 個人 | ・オン・オフの切り替えの難しさ ・通信環境の不安定さ ・設備やセキュリティの制約 ・孤独・コミュニケーション不足 |
| 企業 | ・成果管理の難しさ ・コスト負担の問題 ・労務管理の課題 |
| 地域 | ・インフラと受け入れ体制 ・季節変動による需要の偏り ・継続性の確保 |
デメリットを最小化する工夫
- 事前準備と下調べを徹底する
「市街地で会議、自然エリアでは資料作成」といったように、業務内容と場所を切り分ける計画を立てる。 - 通信環境を二重化
宿泊先の回線だけに頼らず、モバイルルータやテザリングを準備しておくことで不測の事態に備えられます。 - 明確なルール作り
企業は費用負担の基準や勤務時間の扱いをあらかじめ明文化し、従業員に周知しておくことが大切です。 - 地域との共生を意識する
滞在者は地域の生活リズムを尊重し、静かな時間帯の配慮やゴミの持ち帰りなどを徹底することで、地域との信頼関係を築けます。
結びに
日光は自然・歴史・温泉を兼ね備えた魅力あふれる地域であり、ワーケーションの舞台として高い可能性を秘めています。しかし、そこには通信環境の制約やオン・オフの切り替え、地域との共生といった課題も存在します。
スマートワークライフ#Nikkoでは、こうした課題を率直に共有しながら、個人・企業・地域がそれぞれの立場で工夫を重ね、より良い形でワーケーションを実践できる仕組みづくりを目指しています。デメリットを知った上で改善策を講じることこそ、ワーケーションを“理想の働き方”に近づける第一歩です。